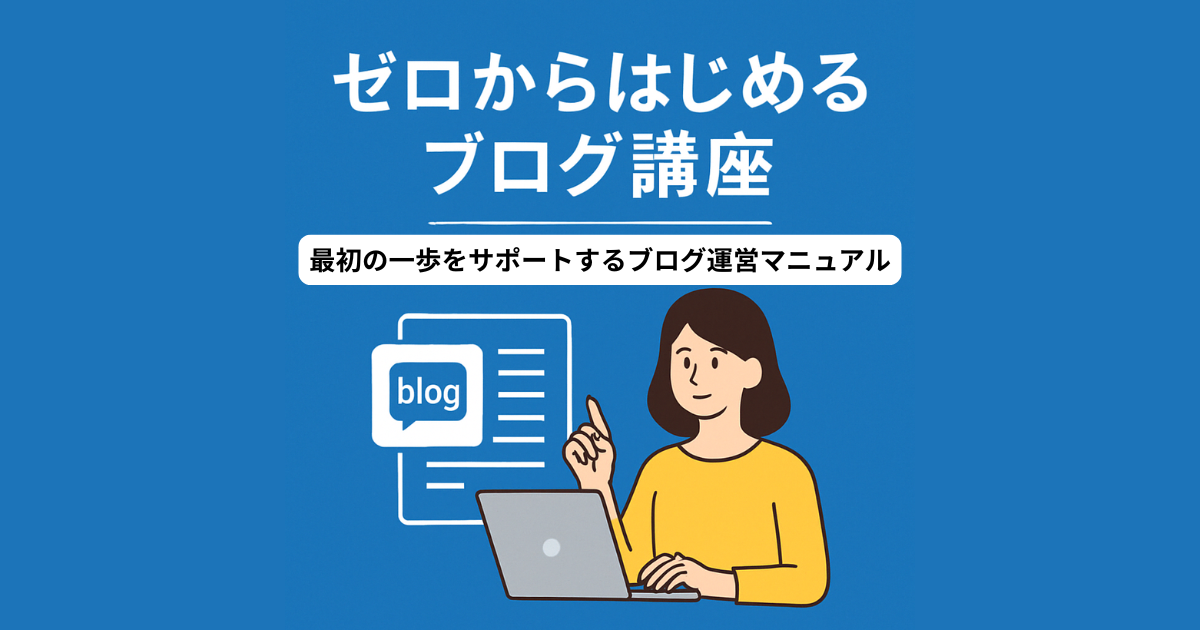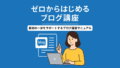ブログを始めたばかりの頃はやる気に満ちていても、時間が経つと「忙しい」「ネタがない」「成果が出ない」などの理由で、続けるのがつらくなる人も少なくありません。
この記事では、そんな“ブログ挫折組”にならないために、無理なく続けるための具体的なコツを5つ紹介します。
1:目標は小さく、行動は具体的に
モチベーションを保つには“成功体験”が大切
目標が大きすぎると挫折の原因になります。
たとえば「毎日3,000文字書く」より「1日1ツイート分書く」でOK。
まずは“できた”を積み重ねていくのがコツです。
「できた」を見える化する
進捗や執筆記録をノートやアプリに残すことで、努力の積み重ねが可視化できます。
これは小さなモチベーションにもなります。
行動目標に変換する
「月に10記事」ではなく「週に2記事」「火曜・金曜に更新」と具体的な行動目標にすることで、迷いが減り、続けやすくなります。
| コツ | 具体例 |
|---|---|
| 目標を小さくする | 「1日1文だけ書く」「3行日記」など |
| 可視化する | 書いた記事数をExcelや日記に記録する |
| 習慣化しやすくする | 決まった曜日・時間に更新する |
2:ジャンル選びは“好き”を優先する
興味がないとネタ切れする
お金になるジャンルだからといって、自分の興味のないテーマを選ぶと、情報収集の時点で苦痛を感じるようになります。 さらに、知識がないジャンルでは内容を深堀りすることも難しく、薄い記事になりがちです。 続けるうちに「書くのがつらい」と感じて手が止まり、そのまま更新が途絶えてしまうケースは非常に多いです。 最初は少しでも関心がある、調べること自体が楽しいと感じられるジャンルを選ぶのが成功のカギです。
日常で考える時間が増えるジャンルにする
普段の生活の中でふとした瞬間に「これって記事にできそう」と思えるテーマは、ネタに困りません。
たとえば子育てや料理、ゲームなど、自分が日々接しているテーマであれば、自然とアイデアが湧いてきます。
テレビを見ているときや買い物中、SNSを見ているときなど、日常のあらゆる場面がネタ探しのチャンスになります。
結果としてブログに向き合う時間が増え、更新が習慣化しやすくなるのです。
テレビや日常からヒントをもらってテーマを決めましょう。
子育て、料理、ゲーム、テレビやSNSでよく見かけるもの、買い物先で見つけたもの、etc…
続けやすさ=“気軽に語れる”こと
ブログはかしこまった文章でなくても大丈夫です。
「友達に話すような感覚で書ける」テーマなら、構成に悩まず、文章もスムーズに出てきます。
話し言葉でアウトプットできる分野は、自分の体験や意見を交えて書きやすく、オリジナリティも出やすくなります。
気負わず書けるテーマを選ぶことで、心理的な負担が減り、長く続けることができます。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 興味があるテーマを選ぶ | 調べる・書くが苦にならない |
| 普段から考えているテーマ | ネタが自然に浮かぶようになる |
| 他人より少し詳しい分野 | 初心者にも優しい記事が書ける |
3:書く以外の作業も「ブログ活動」と考える
書くだけがブログじゃない
情報収集、構成メモ、画像作成、リライト…これらすべてが立派なブログ作業です。
「今日は書けなかった」ではなく「構成を考えたからOK」と考えるだけで気持ちが楽になります。
インプットもアウトプットの準備
本や他ブログを読んだり、ニュースをチェックしたりする時間も、実は記事の質を上げる準備になっています。
すぐ公開しなくてもOK
下書きや構想メモも、未来のコンテンツになります。
「進んでない」ではなく「準備中」と捉えましょう。
| 作業内容 | ブログ活動とみなす理由 |
|---|---|
| 構成を考える | 記事の質が上がる準備になるから |
| 素材を集める | 写真・イラスト・データも重要な要素だから |
| 過去記事を見直す | リライトでSEO改善にもつながるから |
4:完璧を目指さない!60点で公開しよう
完成度より“公開する習慣”を優先
「もっと良くしてから…」「完璧に仕上げたい」という気持ちは誰しもあるものです。
しかし、あまりに完成度を求めすぎると、公開までに膨大な時間がかかり、結果的に挫折してしまう原因になります。
特に初心者は、「完璧な文章を書くこと」よりも「継続して発信すること」を優先することが重要です。
60点でもいいから出す習慣を作ることで、少しずつ成長しながら改善していく方が、長い目で見て良い結果につながります。
「書いて、出す」を繰り返すことで、自然と文章力も構成力も上達していきます。
読者の反応がヒントになる
実際に公開してみると、思わぬ反応が得られることがあります。 自分では「いまいちかな…」と思っていた記事に感謝のコメントがつくこともあれば、力を入れた記事が思ったほど読まれないことも。 読者の視点でのフィードバックを得ることで、自分では気づけなかった改善点や新たな切り口が見えてきます。 つまり、「出してみる」ことが最も効果的なリサーチであり、次の記事をさらに良くする材料になります。
記事は“育てるもの”という意識
記事は「書いて終わり」ではなく、「育てていくもの」と考えると気が楽になります。
一度公開した記事に加筆修正をして、情報を最新のものに更新したり、読者の声を反映して改善を加えることは、SEO的にも評価されやすくなります。
初めは未完成に近い状態でも、読者の反応をもとにブラッシュアップしていくことで、より完成度の高いコンテンツへと成長していきます。
“完璧を目指さず、まずは一歩を踏み出す”——これがブログを続ける秘訣です。
| マインドセット | 説明 |
|---|---|
| 出すことを優先 | 発信を止めないことが継続のコツ |
| リライトを前提にする | 初回から100点を目指さなくていい |
| フィードバックを活かす | 読者の意見がヒントになる |
5:仲間・読者とつながる仕組みを持つ
誰かに見てもらえるだけで頑張れる
ブログを公開したときに「読んだよ」「参考になった」といったリアクションがあるだけで、書く意欲は大きく高まります。
PV(ページビュー)や「いいね」などの数字でも、自分の発信が誰かに届いたという実感につながり、継続のモチベーションになります。
日記のように書いていたブログでも、読者の存在を意識することで、発信の楽しさややりがいを感じられるようになります。
共通の目標を持つ仲間と励まし合う
同じようにブログを続けている仲間がいるだけで「自分も頑張ろう」と思えるものです。
たとえば、SNSで「今週は1記事更新しよう」といった目標を共有したり、お互いの記事に感想を送り合ったりするだけで、孤独感はぐっと減ります。 時には「うまくいってない…」という悩みを共有できる場にもなるので、心理的な安心感も得られ、挫折しにくくなります。
誰かの役に立てることが原動力になる
「ありがとう」「助かりました」といった読者の声をもらえた瞬間、それまでの苦労が一気に報われるように感じることがあります。 たとえ小さな悩みに寄り添った内容でも、誰かにとっては大きな気づきや安心になることがあります。
この“誰かの役に立てている”という実感が、ブログを続けるうえで最強のモチベーションになります。
| つながりの効果 | メリット |
|---|---|
| コメント・感想 | モチベーションの継続に繋がる |
| 仲間とのやりとり | 孤独感がなくなる、情報交換ができる |
| 読者の役に立つ実感 | 継続する意味を見いだせる |
まとめ
ブログを続けるには、技術より「考え方」と「習慣化」の工夫が重要です。 すぐに結果が出ないからこそ、小さな達成を積み重ね、“続けられる仕組み”を自分なりに見つけていくことが大切です。
焦らず、自分のペースで、完璧を目指さず。
“ちょっと書いたら、ちょっと成長”を合言葉に、ブログを無理なく楽しみながら続けていきましょう。